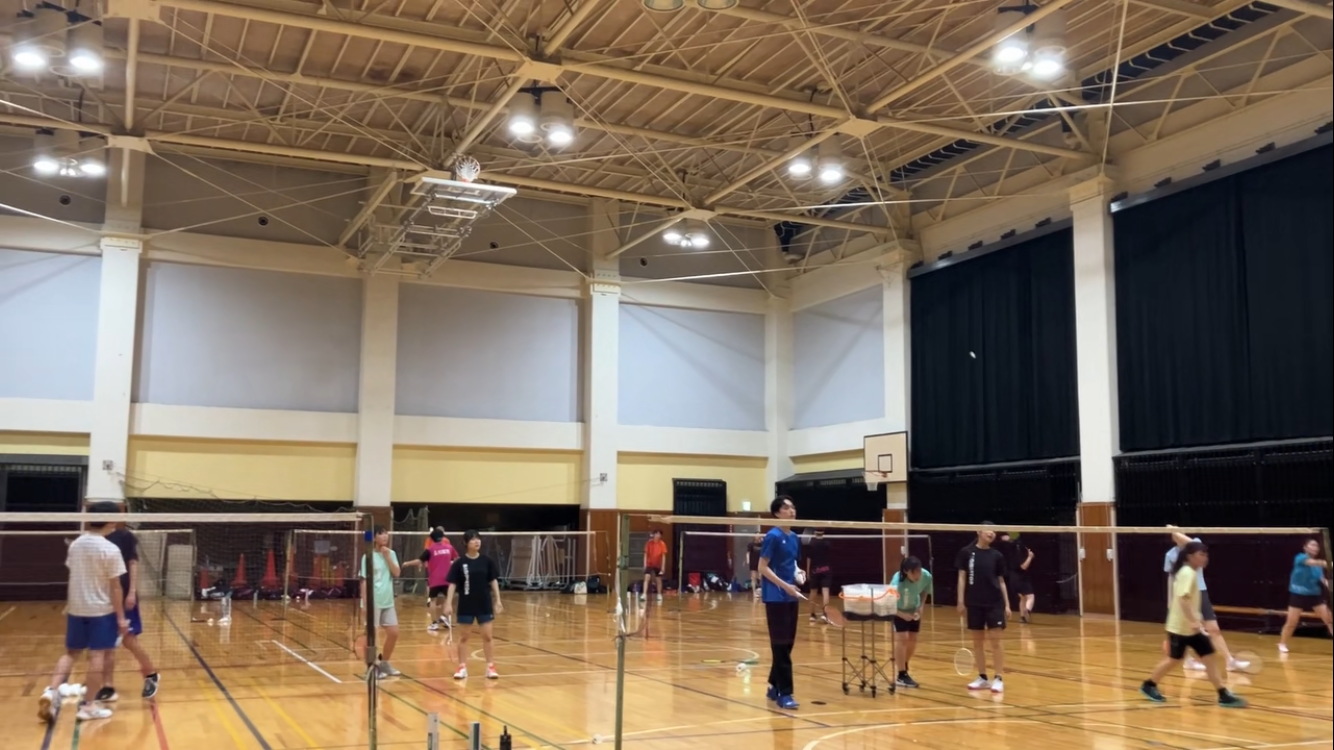【シリーズ第2回】
【シリーズ第2回】
「“ミスしてもいい”は本当?――試合で力を出し切るメンタルの整え方」
――試合中の緊張とどう向き合うか
■ 試合で動けなくなるのは、あなただけじゃない
「練習ではうまくいくのに、大会になると動きが硬くなる……」
「ちょっとしたミスで、頭が真っ白になる」
バドミントンの試合で、こんな経験ありませんか?
実はこれ、レベルに関係なく誰にでも起こることです。
でも、「ミスしてはいけない」と思えば思うほど、体は固まり、逆にミスを招いてしまいます。
力を出し切れない原因は、“気持ちの使い方”にあるのです。
■「勝ち切る選手」に共通するメンタルの習慣――20-18、そこからの1点を取りきるために
🔹その1点が取れないのは「技術の問題」ではない
技術もある、戦術もわかっている。けれど、勝てるはずの試合を落とす。
例えば20-18のリードから、気づけば逆転されている――そんな経験、ありませんか?
相手が急に強くなったわけでも、自分がプレーを大きく崩したわけでもないのに、「あと1点」が遠くなる瞬間。
それは、スキルではなく、メンタルの揺れに原因があります。
🔹「勝ちたい」が強くなるほど、体は守りに入る
・打てていたスマッシュが置きにいく
・プッシュが弱くなる
・ヘアピンが浮く、また入らなくなる
・一歩目の反応が遅れる
終盤、選手の多くが「守るようなプレー」になってしまいます。
これは、「ミスしたくない」「勝ちたい」という思いが強くなりすぎたことで、無意識に体が守りのモードに入ってしまうからです。
「攻める勇気」より「失敗を避ける心理」が勝ってしまう――
この状態を避けるためには、事前の“心の準備”が不可欠です。
■ 上級者ほど実践している「自分ルール」の習慣
試合で勝ち切る選手は、**自分なりのルール(思考スイッチ)**を持っています。
たとえば:
-
「18点以降は、1点ずつ“0-0”のつもりで戦う」
-
「ミスしてもガットを直しながら表情を保つ」
-
「“勝ちにいく”ではなく“自分を出し切る”と唱える」
このように終盤のプレッシャーに対して“反応ではなく選択”できる状態をつくっているのです。
逆に、自分ルールがないと、流れや感情に飲まれてしまいがちになります。
■ 「ミスしても攻め続ける胆力」が勝敗を分ける
“ミスをしない”ことを目指すと、プレーは縮こまりやすくなります。
でも“攻める中でのミスはOK”という前提に切り替えられれば、選手は自信を持って動けるようになります。
実際、勝ち切る選手ほどミスに対する耐性が高い。
それは、成功体験だけでなく、「ミスを乗り越えた経験」を積み重ねてきたからです。
私が現場でよく選手に伝えている言葉:
「攻めのミスは“勝ちにいく過程”。結果より“意図”に集中して、すぐ切り替えよう。」
「19-19から“本当の勝負”。“今ここ”に集中しよう。」
このような“考え方の習慣”が、**終盤に必要な「攻める胆力」**へとつながっていくのです。
■ 試合の終盤を支配する「セルフコントロール力」
終盤は、技術・体力・戦術のすべてが出そろったうえで、
「自分をどれだけコントロールできるか」が勝敗を分けます。
-
勝ちたい気持ちに飲まれない
-
ミスを引きずらない
-
1点ごとに心をリセットできる
このセルフコントロール力も、才能ではなく習慣で身につけることができます。
 【今日からできる!切り替えヒント】
【今日からできる!切り替えヒント】
ちょっとしたルーティンを作ることで、メンタルの切り替えがスムーズになります。
-
呼吸を深く1回する:息をゆっくり吐くだけで、緊張がリセットされる
-
言葉で整理する:「次いこう」「今に集中」など、シンプルな声かけ
-
体の動作を入れる:ラケットをくるっと回す、背筋を伸ばす など
練習からこの習慣を取り入れておくと、本番でも自然に切り替えができるようになります。
■ メンタルを整える3つのヒント
-
「ベストの自分」より「今の自分」を信じる
→「今日はこれで戦おう」と決めることで、迷いが減りプレーが安定します。 -
ミスをしたら“リセットの合図”を決める
→ ガットを直す、呼吸、言葉など、自分の“切り替え動作”を習慣化する。 -
緊張は悪くない――集中力のスイッチと捉える
→ トップ選手も緊張します。それを“良い緊張”として利用できるかがカギです。
■ おわりに:コートに立つ自分を信じるために
バドミントンは、技術だけでなく気持ちの持ち方で結果が大きく変わるスポーツです。
たとえ勝てなかったとしても、「最後まで挑戦できた」「自分に勝てた」と思えるなら、それは確かな成長です。
大会前は、自分に少し優しく、
そして、コートに立ったら――
“いつも通り”じゃなくてもいい “今できるベスト”を出し切る自分でいましょう!
 次回予告【シリーズ第3回】
次回予告【シリーズ第3回】
ラリーは情報戦
――“読み・誘い・崩す”配球術で主導権を奪え!!
■ 強打だけがラリーを制するわけではない
ラリーで主導権を握るために必要なのは、派手なスマッシュや決定打ではありません。
**“どこに・なぜ打つか”というショットの組み立て(=配球)**こそが、試合を左右するカギになります。
■ 配球は「相手との会話」
攻撃パターンを繰り返すだけでは、すぐに相手に読まれてしまいます。
逆に、“相手の反応”に合わせて組み立てを変えることができれば、ラリーの流れを自分で作ることができます。
次回は、「配球=相手との会話」という視点から、
ラリーを“打ち合い”ではなく“読み合い”に変えるヒントをお届けします。
お楽しみに!!